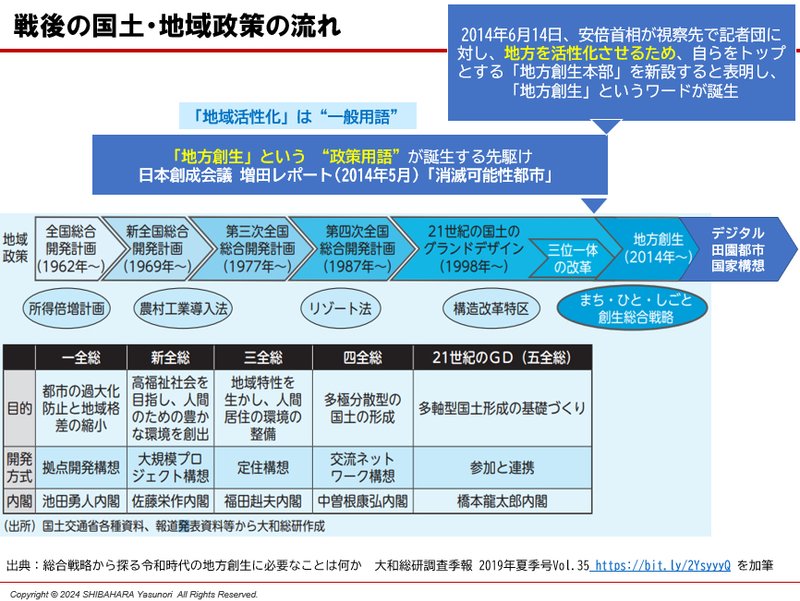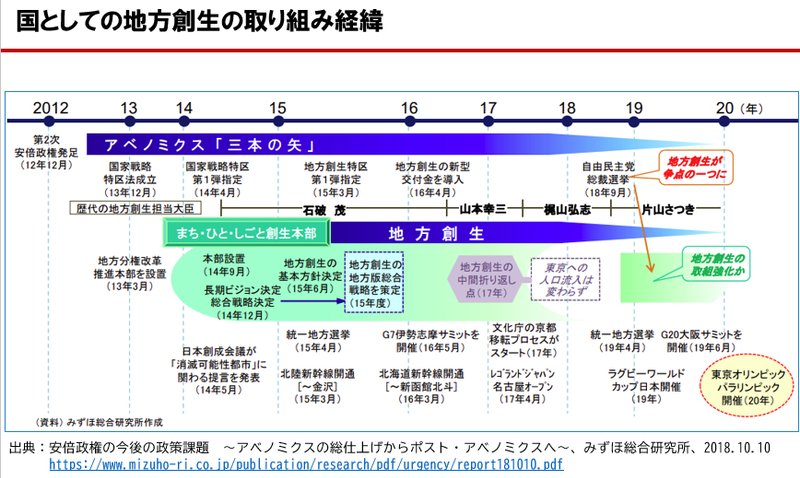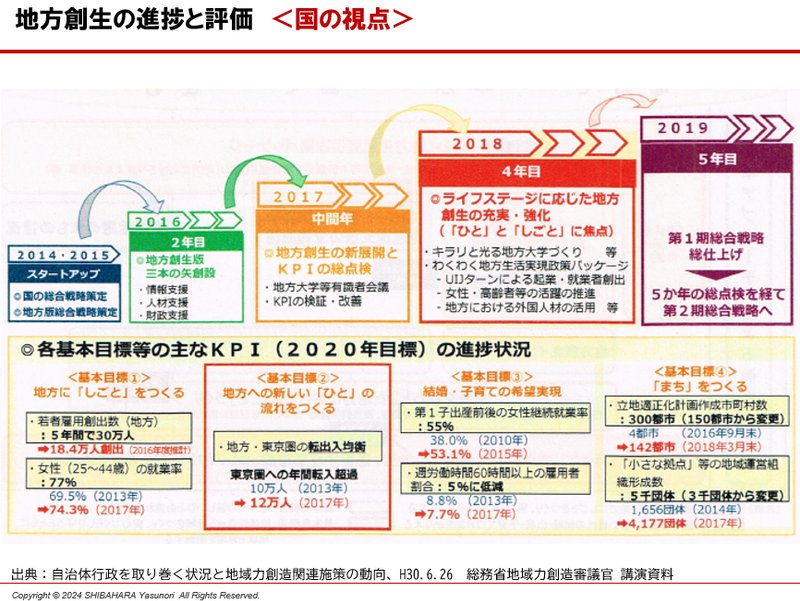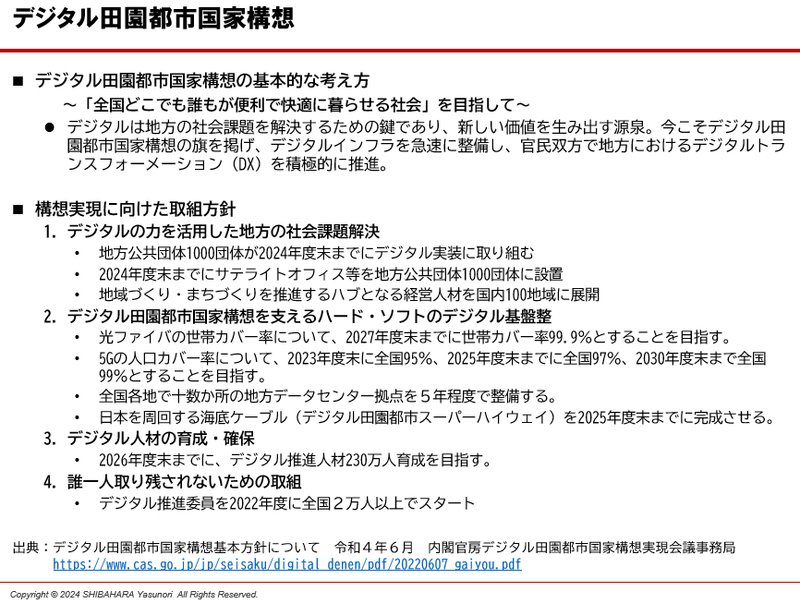政策動向
最近、社会的孤立・孤独が社会問題化している。社会的孤立・孤独の構造的背景として、社会経済の低迷(可処分所得が伸びない)、雇用形態の変質(将来が安定しない/希望が持てない非正規雇用の拡大)、生活環境の変化(デジタル化)、人口・世帯構造の変化(人口減少、少子高齢化、核家族化、未婚化・晩婚化、独居高齢者増加)等に伴い、働き方、住まい方、暮らし方が変化し、従来の地縁・血縁等の「人のつながりの希薄化」の進展が基底にある。
そうした急激な構造的背景が相まって進行している折に、2019年(令和元年)末から、コロナ禍が発生し、国際的な移動の遮断、そして国内的には一斉休校措置、休業要請、外出自粛要請が行われ、非正規雇用者を中心に雇用環境の悪化、加えて各種の社会的支援活動も縮小・停止に追い込まれ、生活/経済弱者を中心に大きな影響(例えば、家族や周囲の人に相談ができずにひとりで出産したのちに乳幼児を遺棄した人やヤングケアラー、介護殺人、虐待、自殺等)が出た。加えて、自宅での時間が増えたことは、家族/家庭内での過ごし方の変化をもたらし、コミュニケーションや相互への理解が向上する反面、逆作用の問題を励起・顕在化させた。
こうした事象の顕在化が「社会的孤立・孤独」を社会問題として認識さすことになり、2021年(令和3年)2月に「孤独・孤立対策担当大臣」を指名して同大臣が司令塔となり、内閣官房に「孤独・孤立対策担当室」を設置した。同年3月以降、孤独・孤立対策担当大臣を議長とし、全省庁の副大臣で構成する「孤独・孤立対策に関する連絡調整会議」を定期的に開催している。
2021年(令和3年)6月には、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」が閣議決定され、2024年(令和6年)4月1日、「孤独・孤立対策推進法(令和5年5月31日成立 令和5年6月7日公布)」が施行されるに至っている。
孤独・孤立対策推進法
Act on the Advancement of Measures to Address Loneliness and Isolation
(基本理念)第一条 この法律は、社会の変化により個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態(以下「孤独・孤立の状態」という。)にある者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組(以下「孤独・孤立対策」という。)について、その基本理念、国等の責務及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とする。
(基本理念)第二条 孤独・孤立対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること。
二 孤独・孤立の状態となる要因及び孤独・孤立の状態が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(以下「当事者等」という。)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを旨とすること。
三 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われるようにすることを旨とすること。
出典:孤独・孤立対策 内閣府
参考:孤独・孤立対策の重点計画 令和3年12月28日 孤独・孤立対策推進会議決定
参考:日本における孤独・孤立の現状と対策 堀 純子 / 国立国会図書館調査及び立法考査局専門調査員 議会官庁資料調査室主任 レファレンス(The Reference) 2023-2-20 国立国会図書館 調査及び立法考査局




 令和6年
令和6年